夏野菜の時期ですね。
早く来ないかなーと思っていたら、もう4月の半ば。早い。
私はすごく狭いお庭で楽しんでいるのですが、去年は連作障害でしょうね!な感じにトマトがあまりできなかったのでショックでした。
症状としては大きくならない、実があまりつかない(トマトなのに!)です。
そう、この連作障害。
話には聞いたことはあるのですが、時折見かける他の方の畑は同じようなものを毎年植えているように感じていたのでそんなに重く考えたとこはなかったのです。
ですが、前回が結構ひどくて。反省して今回は少し本腰入れたいと調べてみました。
連作障害とは
連作障害とは
同じ土地で同じ作物を栽培することで、成長が悪くなったり枯れてしまうものを言うようです。
原因は同じ作物を何度もそこで栽培すると同じような栄養を消費して、残す栄養は蓄積されたままなので、同じ作物を植えることでその作物が好きな病原菌や、害虫が寄ってくるなど、いろいろ良くないことがあるそうです。
起こりやすい連作障害の病気など
青枯病
土壌の細菌が原因の病気で傷がついた根っこなどから病気が入り込みます。
感染した植物は、日中はしおれますが、曇りや、夜間になると回復します。
その後徐々に株全体が緑色にも関わらず枯れていきます。
萎黄病
原因は土壌にいるカビや、昆虫(ヨコバイなど)によって運ばれた細菌によって感染します。
症状は葉の一部が黄色く委縮して、最悪枯れることになります。アブラナ科の野菜に多い印象です。
つる割病
酸性土壌や、窒素成分を多く与えたときに発症しやすくなります。
原因はフザリウム菌と言われています。
症状はウリ科、サツマイモ、朝顔などに発症して、葉っぱは黄色く変色して、茎などは縦に裂けたり、茶色くなり枯れてしまいます。
根こぶ病
アブラナ科の植物特有の病気です。
症状としては根っこにいびつなこぶがたくさん形成されて、成長阻害されます。
この病気になるとその地域の土壌ではなかなか発生させない対応が難しくなりますので、起こさないことが最重要となります。
アブラナ科の野菜の連作で発症の確率が上がります。
線虫害(センチュウ)
土壌に生息し、野菜に寄生することでその野菜の育成を阻害し、育成不全、収穫量の低下を招きます。
ネコブセンチュウ{根っこにこぶを作ります。症状は上記根こぶ病と似ていますがアブラナ科以外にも 発症します。
ネグサレセンチュウ{根っこに障害起こします。根腐れを起こします}
シストセンチュウ{根っこにシスト(休眠上のさなぎのような状態にセンチュウが根っこに寄生している)を作り多数の硬い球状のものを形成します。
他、たくさんのセンチュウがいます。
作物による連作障害の起こりやすさ
連作障害を起こしやすい物
ナス科(トマト、ナス、ジャガイモなど)
ウリ科(きゅうり、ゴーヤ、スイカなど)
アブラナ科、マメ科 などなど
連作障害を起こしにくい物
ネギ科(ネギ、玉ねぎなど)
サツマイモ、かぼちゃ、ミョウガなど。
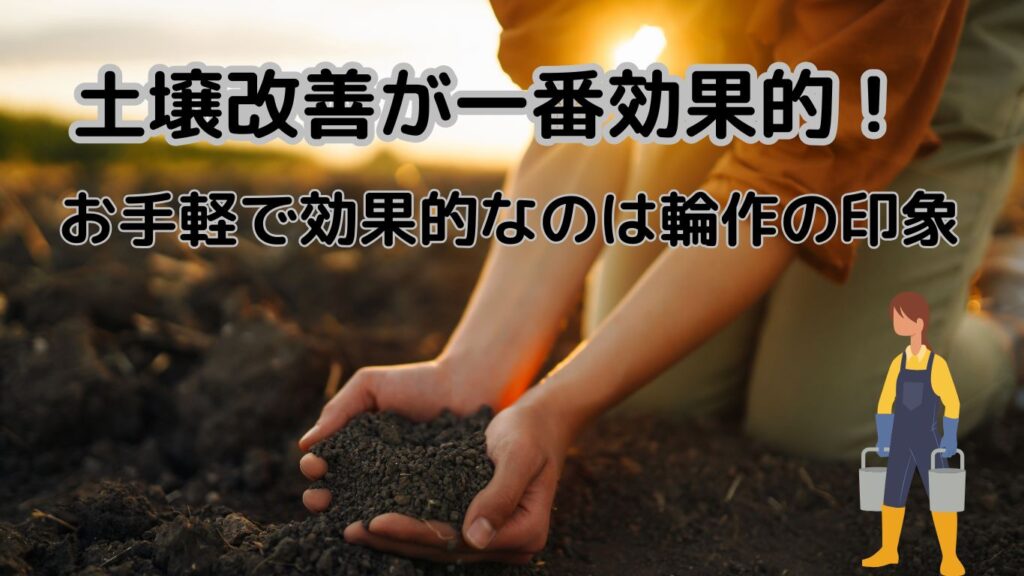
連作障害の対策はどうすればいいのか
適切にその土地の状態を診断して、必要な栄養分のバランスをとる
虫、病気対策を行う
その土地は暫く使わない
気になる連作障害の対策は
有機物や堆肥、米ぬかなどを土に混ぜ込み、土壌の改善を図る
堆肥や、腐葉土などを土に混ぜ込むことで微生物が生活しやすい環境を作り、バランスを整えて病害虫に強くする方法です。
太陽熱などの熱消毒を行う
土壌の病原菌、虫を退治するために夏の暑い日に熱湯を土にたっぷりとかけて、そのうえでビニールで覆い高温に土を保つことで、病害虫を抑制する方法です。
緑肥を行う
土壌の色々なバランスが悪くなっているため廉作障害が起こるので、この土地にイネ科やマメ科の緑肥を植えて成長、その後土にすきこみ、土壌の改善を行う方法です。
よく参考にしている輪作の中でのクローバーは、マメ科で、このノーフォーク農法でも採用されてるようです。
☆ノーフォーク農業{大麦、クローバー、小麦、かぶを順番に4年周期で輪作します。}
連作年限に注意して小さい畑、庭でも選んで家庭菜園
同じところで同じようなものを植えることが連作障害の原因ですから一番はやはり同じものを毎年同じところで育てないことが一番です。
しかし、野菜の特徴によりあまり期間をおかずに植えて大丈夫な野菜と数年植えない方がいい野菜が存在します。
例えば家庭菜園で最も育てられているだろうトマト、なすなどは3~4年と言われています。以下下記にて分かる物をまとめました。
1年程度
ほうれん草、カブ、キャベツ、大根、小松菜、ニンジンなど
2年程度
白菜、レタス、インゲン、キュウリ、ジャガイモ、サツマイモなど。
3~4年程度
トマト、ナス、ソラマメ、里芋など。
4~5年程度
エンドウ、スイカなど。
ネギ、タマネギなどは比較的連作可能と言われています。
また、耐病性のある接ぎ木での連作障害対策も良いとされていますので選択肢に入れてもいいかと考えますが、やはり一番確実なものは輪作かな、という印象です。

小さい庭、畑の私の家庭菜園での連作障害を考える
やはり小さな限られた庭、畑での家庭菜園は色々な土のバランスも考えつつ取り入れやすいのは、ノーフォーク農業のように大麦、クローバー、小麦、カブと言う感じに作る作物を変えていく手法かなと感じました。
ちなみに初めは18世紀のイギリスでの農業だそうです。すごい昔からみんな困っていたのですね。連作障害。農民からすれば本当に死活問題。
私の狭いお庭にも少し考えて植えましょうか、というわけですが。本当に狭い土地なのでまず、育てたい野菜はトマト、オクラ、ピーマンです。
このうちトマトとピーマンが同じナス科なので注意ですね。
基本的に同じ科で連作障害のなりやすさ、開けておいた方がいい期間が似ているようなので、そのくくりで考えたいともいます。
トマト、ピーマン、の後には何か植えたいので、調べてみますとアブラナ科のキャベツ等、ネギ科の玉ねぎなどおすすめされましたので、また秋口ぐらいに悩もうと思います。
でも、アブラナ科は虫が来る印象で二の足を踏んでしまいそうです。青虫。
で、オクラはマメ科をおすすめされたのですが、枝豆とかですけど、これ4月5月に苗を植えるって書いてまして。一年後の話ですか、、、。秋口に何か植えたいのですが、、、。
ということで、比較的連作障害になりにくいかぼちゃをここで植えてみようかな、とチャレンジ予定です。
一応ポリポットに育苗して置き適切な時期に植えてみようかと思っています。
予定ですので、変更は大いにあると思いますので、大きな心で見ていただけると嬉しいです。
それにしても、連作障害は私の狭い庭では難しい問題ですね。
育ちのこともそうですが、病原菌、虫問題がとても厄介に感じます。
多分、前回今回根切り虫?ヨトウムシの被害受け中なんですが。
なんですかね、あの虫。
ひまわりの双葉を毎晩切るんですけど。茎ごと。今はプラカップに避難させていますが、これからどうすればいいのか。
農薬使わなければいけませんかね、、、。
虫についてはある程度大きくなると効果がないようなので、これも悩ましいところです。
まあ、今年も家庭菜園楽しんでいきたいと思っています。
少し、追記、変更しました。2025.6.28



コメント