最近の謎なのですが、このブログを見てくださっている方ならばご存じの通り、何度か白菜の苗づくりを失敗している私です。早々に虫にやられます、、、。
それで、今年は白菜をあきらめて大根を種直播で、初めから不織布という結構頑張った虫対策を行っていたんです。
私の手持ちの中で、ですが不織布は防虫ネットよりも細かい虫をシャットアウトできますし、個人的に葉っぱが食べたいので葉っぱを綺麗に収穫したくて。

でも、最近少しの虫食いが。
最近は結構寒くなってきたので虫はいないイメージですが、、、。
もちろん不織布は今もしています。なんの虫食い、、、。
防虫ネットとは何か?基本的な機能を解説
その名の通り防虫ネットは虫を(場合により鳥などのシャットアウトも)作物に付けないためのメッシュ構造の布です。
結構昔から特に家庭菜園者に愛用されており、できるだけ農薬を使いたくない気持ちを体現してくれるありがたいアイテムです。
その防虫ネットの種類も様々で、目の大きさも対する虫などの大きさに準じて違ってきますので、購入する場合は目の大きさがポイントになります。
また、色も主に赤、黒、白などがあり特に赤色の防虫ネットはアザミウマが嫌う色として有名です。
白が主に使われていますが、この白色の防虫ネットは光を通しやすく、日照不足を起こしにくく、防寒、防霜にも有効とされています。
黒の場合も特定の虫に有効とされていますし、夏場には遮光効果を期待してなど、そういう理由で使うこともあります。
他にも、単一の色ではなく、防虫ネットにシルバーのラインが入っているものもありこれは光の反射効果で虫が嫌がるとされています。
素材も種類がありますが、値段や耐久性の違いがありますので、長く有効に使いたい場合はそこも選別の一つになります。
防虫ネットを使うときの選び方
野菜を作る場合は多分初めに調べて野菜を育てていると思います。
そして調べていくうちに、この野菜はこの虫が付きやすいんだな、もしくは一度虫に攻撃をされて調べていくうちにこの虫が悪さをしているんだな、と気づく場合もあります。
この場合に農薬を使わずに対処したい場合に、行きつくのはこの防虫ネットになることが多いですよね。
でも、防虫ネットは意外にいろんな種類がある。
この場合はまず、何を防虫したいか、どんな季節に、野菜はどこまで大きくなるか、どのサイズか、が選別の大切な項目になります。
ですので、モンシロチョウだけを防御したい時とアブラムシを防御したい場合は網目の大きさが番ってきます。成虫の大きさが違いますので。
小さければなんでもいい、では無くて、目の大きさが小さいほど通気性、遮光性などが低下してしまうので、そこも考慮して適切な防虫ネットを選びたいですね。
虫食いが発生する理由(防虫ネット使用時)

不思議に思う防虫ネットをしたのに虫食いが起こることがあります。現に私は起きています。ホラー。
この場合はやはり原因がありました。
ネットの破損があり、そこから侵入した
繊細な作りをしている防虫ネットですが、意外に扱ってみると結構頑丈な手触りです。
このため油断しがちなのですが、やはりメッシュ構造ということもあり、鋭利なものや何々引っ掛けたときに意外に穴が開いたり切れたりすることがあります。
また購入時は頑丈だとしても、数年使うことにより、太陽光や、雨風などの環境変化により経年劣化も起こることが多いです。
このため気が付かないうちに、穴などができてそこから害虫が侵入、食害に至ることがります。
防虫ネットがちゃんと張られていなかった
防虫ネットはちゃんと作物をぐるりと保護できるように、隙間なく張ることが重要ですが、初めの張りが甘かったり、環境の変化で隙間ができてそこから虫が入り害虫被害にあうことがあります。
また、初めは大丈夫だろうと思い双葉が出そろった時点で、防虫ネットを張る場合も知らぬ間に双葉の時点で害虫が卵を産み、後々成長して防虫ネットの中でムシムシ天国が出来上がることがあります。
こういう場合も考えて、特に虫被害が多い作物、例えばアブラナ科などは種植えから防虫ネットを張ることをお勧めします。
防虫ネットを少しの間でもひらきっぱにしていた
害虫はおいしい野菜を日々自分の赤ちゃんの為に狙っています。
その為、少しの野菜の日光浴に、と少し開けて人間が離れている間にするりと害虫が侵入して卵を産み付けることがあります。
出来れば、防虫ネットを完全に時期以外はあまり開閉したくないところではありますが、季節などの状態によりそういうこともできませんよね。
ですので、水やりの必要性があるときも素早く作業を行い、又完璧に防虫ネットで作物を保護したいです。
土の中にもういた、、、
意外なところで実はもう土の中に害虫がいて、そこに種を蒔きネットをしたということも考えられます。
軽くホラーな気分になりますが、完璧に種を蒔いたあとに、完璧に作物とネットのサイズを考えて、完璧に防虫ネットを行い、完璧にしていたはずなのになぜか虫がいる。葉っぱの害虫被害が起こる、、、。きゃーーーー!!
この場合はもう初めから土の中に幼虫、あるいは卵がいて孵化してネットの中で害虫被害が起こっている可能性があります。
害虫はひらりと空や草原以外にも土の中にも潜んでいる場合があります。
主に、コガネムシ、ネキリムシ、ヨトウムシなど。他にもダンゴムシ、カタツムリなども土に紛れている場合もあります。
対策としては、種を植える前によく土を耕し、そして害虫を除去する、夏場などでしたら日光熱を利用した消毒を行う、農薬を使うなどが主に使われます。
結構盲点ですが、新品の培養土に、プランターで植え付ける場合意外は虫の卵や幼虫以外もいる可能性を考えた方が失敗が少ないです。
もちろんこの場合の培養土の品質は大切です。
品質が良くても長期軒先に放置していた場合は、その長期間のうちに空気穴などから虫が混入することもありますし、品質があまり良くない培養土は初めから虫が混入していた話も聞きます。
そしてネットを張っていて害虫が発生した場合は、作物の根元や葉っぱの裏など重点的に探してください。ネキリムシ、ヨトウムシ、ダンゴムシ、ナメクジなどは株元、葉っぱの裏などにいることが多いですので。
そして、作物が元気がない場合は根っこがやられているかもしれません。悲しいですが。
ネットに作物が触れてそこに卵を産まれた
作物が育っていくうちに、想像以上に大きくなり、防虫ネットの中でキュウキュウになることが時々あります。
そのままにしておくと、意外にそのキュウキュウになった場所のネットに接触している葉っぱに害虫が卵を産み付けて、中で幼虫になり、虫食いが発生することもあります。
防虫ネットは防御したい害虫の成虫を想像して目の大きさを選び、ネットを張ることが多いですが、当たり前ですが、成虫のサイズより卵のサイズの方が小さく、予定した目のサイズをすり抜けることがあります。
この場合もネットの中でムシムシ天国になることになりますので、野菜がネットに引っ付きそうな場合は速やかに余裕のあるサイズに変更したほうが失敗が少なくなります。
小さな幼虫が侵入した
こちらは稀ですが、周りに雑草が多い場合や、対象にした害虫の幼虫が近くにいる場合に、まれに小さいサイズのまま防虫ネットをすり抜けて(小さいので)防虫ネットの中で大きくなることがあります。
このようなことが無いようにできれば守りたい作物の近くには雑草や虫がよく寄るような作物(放置中)は無い方が無難です。
意外に、害虫は行動範囲広いですよ。見ていると結構芋虫でも歩くの早くて怖くなりました。
まとめ

家庭菜園者では無農薬でのチャレンジには欠かせない防虫ネットですが、やはりアイテムですので、使い方により防虫ネットを張っていてむ虫食いが出てくることがあります。
よくあるのは知らぬ間に穴や、ちゃんと張れていなかったため虫の侵入を許してしまったことですが、意外なところに張る前から虫が居たり、少しの間にも虫が卵をうっ見つけていたり、想像以上に野菜が大きくなりすぎて防虫ネットの役目を果たせていなかったりと様々な理由がありました。
私の場合も、途中の防虫ネットの開閉で虫の侵入を許してしまったようです。
油断はできませんね。害虫対策。
この頃寒くなったとはいえ、場所によりちょうちょもまだ見かけますので引き続き防虫対策に気を付けたいです。

今年も終わりが少し見えてきましたね。お体を皆様お大事にして楽しい家庭菜園ライフをたのしみましょうね
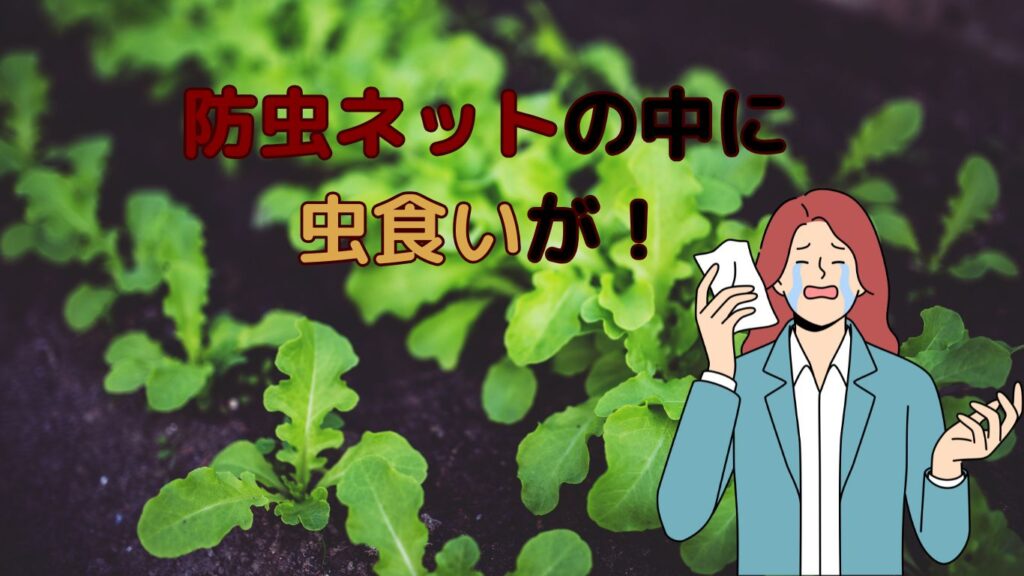

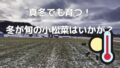
コメント