9月に入りましたが、まだまだ暑いですね。
個人的に私は頭痛持ちなので、こうも暑さが続くと辛いです。そして、夕立が来る前から頭痛がする体質なのですが、それでも夕立が来てほしいくらい雨がないですよね。これもつらい。
一応毎日水やりを行っているのですが、野菜たちもつらいと思います。
でも、私の家庭菜園の中で今一番元気なオクラ。あの野菜の花と思えない大き目のオクラの花に日々癒されるのですが、実は花芽、新芽あたりが食い荒らされていて、、、。犯人は?
オクラの概要
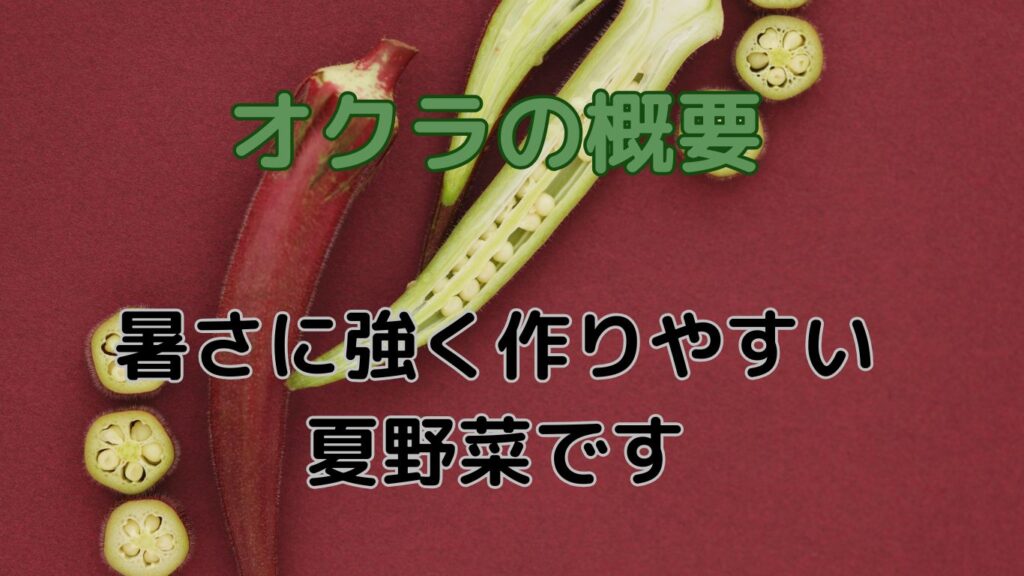
オクラは夏野菜で、夏の暑さには強めですが寒さには比較的弱いです。
栽培適温15~30度ぐらい。
5月~6月初旬に種まきを行い、育てることが多いですが、場合により7月ぐらいでも種まきを行い育てることも可能な夏に強い野菜です。
収穫は7月~10月ぐらいで、夏野菜ですので10度以下になってくると、成長ができなくなってきます。
お花はきれいな大き目の花が咲き、野菜たちの中で一番きれいなんじゃないかな?と思います。
その花が落ちると見慣れたオクラの赤ちゃんがいます。
オクラの赤ちゃんは早いと一日2センチぐらいのスピードで大きくなるのでびっくりです。
丸オクラだと少し遅めでも食べれますが、そうでないとゴリゴリにすぐ大きく筋張ってきます。
切るとねばねば、栄養満点のオクラ料理にお使いください。
ねばねばの正体は食物繊維ですので、おなかの調子を整えたり、ダイエット効果も期待できます。
ビタミンやβ―カロテンなども含まれており、この暑い夏を乗り切るためにも必要な栄養素ですね。
ワタノメイガとは何か?(ハマキムシとも)
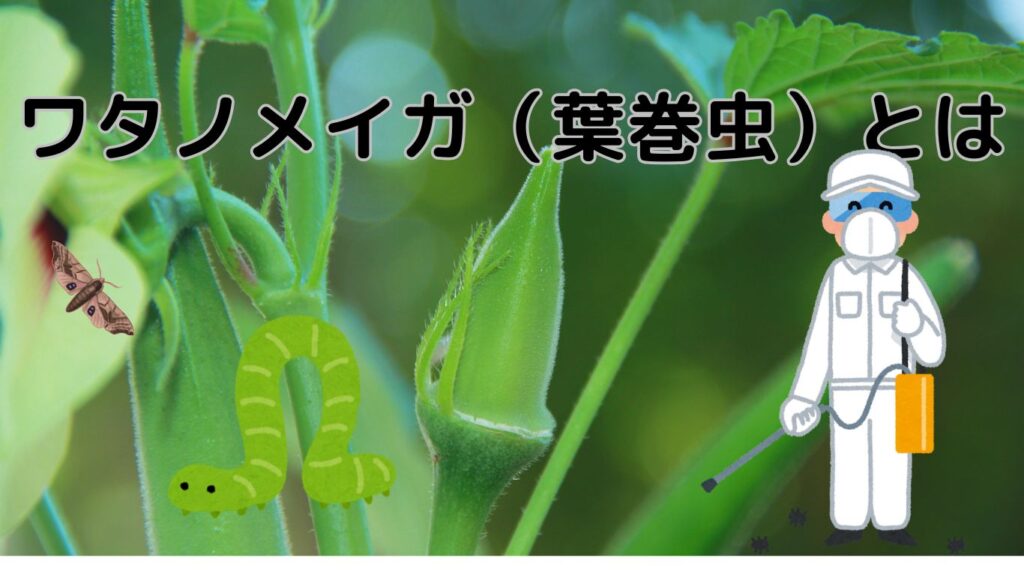
チョウ目・ツトガ科の害虫です。
春から秋によく見かけます。私はオクラ被害が毎年あるので、オクラ育てている方は見たことがあると思います。ピークは7~9月。
別名の通り、芋虫の幼虫時期に好みの植物のアオイ科の植物の葉っぱを葉巻状にして食害します。
成虫の大きさは大体2センチ程度です。
外から見ると、葉っぱがくるりと撒いており不思議な感じに見えます。
この上からは薬剤散布はあまり効果がなくて、その場所を切り取るか、くるりと撒いたところを戻して、害虫に薬剤散布、除去するかになることが多いと思います。
私は切り取っています。
葉っぱを蒔いて少し食べるだけなら、、、と思いますが、葉っぱを蒔くことで光合成が阻害されるのであまり良くはありません。中にいっぱいフンも入っていますし。
見つけたら対処しましょう。
よく似た名前のアワノメイガ
欲に名前にアワノメイガという虫がいます。害虫ですね。
こちらは主にトウモロコシ栽培の厄介な害虫になります。
メイガ科に属する蛾で、トウモロコシのひげあたりから実の方に潜り込み食害します。
北海道付近では1回ぐらいの流行が多いようですが、温かい地域でしたら4回ぐらい発生することがあるほど、厄介な虫です。
こちらも侵入防ぐために防虫ネットや、薬物散布を行い予防することが多いようです。
私は今まで見たことが無いのですが、トウモロコシと言ったらこの虫ぐらい有名な害虫です。
効果的なワタノメイガ対策
ワタノメイガの成虫は、夜にターゲットとなるオクラの葉っぱに卵を産み付けます。
この卵は一見水滴のような見た目で、しかもとても小さく、一個一個ばらばらに産み付けるという発見の難易度の高い卵です。
防虫ネット対策
産み付ける前に防虫ネットで囲うことが一番効果的です。
冬越しは、枯れ葉の下でやり過ごすことが多いようですので、防虫ネットを行う場合はオクラ以外の物を除去して、(枯れ葉や、草などが混入しないように)できるだけ早めに行うことがいいとされています。
ネットのサイズは1~2㎜程度のもので、成虫をシャットアウトできそうです。
発見時に対処する(捕殺、排除)
分かりやすく葉を巻いているので、そのような場合はその部分だけ切り捨てる。
もしくはゆっくり葉巻を解き、中の害虫を捕殺することになりますが、この場合意外に幼虫が素早く動き、糸を吐いて葉っぱより落ちることがありますし、葉を巻きつつ排せつ物もその葉っぱに蓄積されているので、注意です。
このワタノメイガ自体に毒性は持っていないとされていますが、アレルギーなどはわかりませんので、直接除去する場合はご注意ください。
薬剤を使う
余りにも被害が多い場合は、薬剤も使うことができますが葉巻という特性により浸透移行性のあるお薬が効果があると思います。
農薬を使う場合は用法容量を守り正しくお使いくださいね。
オクラに付く透明の粒は虫の卵?
オクラを育てている上で害虫問題は出てくるとは思いますが、害虫でなくても卵のような粒がオクラには着くことがあります。
オクラの汗ともいわれているもので、見た目は水の小さい水滴のような外見をしていますが、触ると弾力があるような?ポロリと落ちます。
これはオクラのねばねば成分などが、外に出てきたものとされています。
特に病気や弱った時にオクラから出るみたいなこともなく、普通によくある生理現象のようです。
まさにオクラの汗ですね。
でも、虫の卵と紛らわしくもあります。オクラを観察してみましょう。
葉っぱなどに食害された後はありませんか?
正常の範囲でオクラが色も変わらず成長できていますか?
特に変わりない場合は、オクラの生理現象の物の可能性が高いと言えます。
新芽、花芽などが食害さ入れている
ここからは私の推察になるのですが、このワタノメイガが発生する前にオクラの新芽、成長点ふきんを何かが食害している様な感じがするんです。
居ても小さいのでしょう、よくわからないけど、少し糸?が張るような、何かのフンがあるような。すこし新芽ふきんが茶色っぽく変化してしまうんです。
その状態の後に大きくなる葉っぱがすごい穴あきで、成長するのでやはり何かがいたのだろう、ああ、葉巻が多く出来てる、、、。というような感じで。
しらべるけども、葉を蒔く状態のワタノメイガの性質が分からなくて。卵からかえった後は、新芽の柔らかいものを集中的に食べているのかな?とも考えます。
他に虫がいるような気配はないですし、明らかに食害されているのでアブラムシやカメムシなどの栄養を吸う虫でもないでしょう、、、。

私の中で、ワタノメイガのせいにして今日もロハピをかけています。
そうすると、それ以上の被害は食い止められている印象です。その時に被害があっただろうひどい穴あきの葉っぱが展開していくことが悲しいですが、しばらくすると通常の新芽、花芽になるので、毎年様子見になっています。私ごとですが。
追肥で新芽を健康に育てる
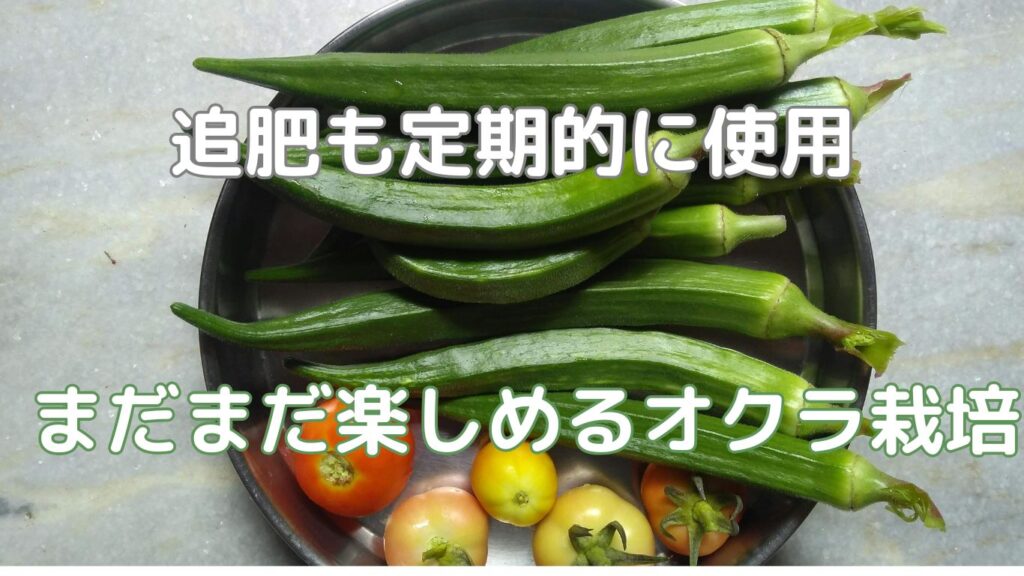
オクラは季節があえば、次々と新しい花を咲かせて実になってくれます。
でもその分だけ、栄養も必要とします。
一般的に元肥料で育てていき、一番果ぐらいができたごろより追肥を始めます。
ペースとしては、使う追肥の種類によりますが、月に1.2回程度です。
化成肥料や、有機肥料なんでも大丈夫ですが、液肥の場合は回数を少し多めに週に1.2回は行います。
株元すぐにまとめて肥料を追肥すると、肥料焼けで病気になる可能性があるので、少し株元より離してぱらぱらと追肥してあげてください。
その後の水やりもお忘れなく。
オクラは肥料が少なすぎると、葉っぱが細く小さめに、色も少し薄めになり、そして葉っぱの切込みもきつめになります。
正常な花の位置は、上の成長点より葉っぱ三枚程度の場所で咲くと正常と言われています。
しかし、肥料不足ですと成長点に近い場所で花が咲くようになってきます。
こういう状態がある場合は肥料不足の可能性があるので、追肥を行ってくださいね。
多すぎても少なすぎてもいけませんが、せっかくの夏野菜おいしく食べるためにも追肥を欠かさないようにしましょう。
おくらおすすめレシピ(オクラのお浸し)
個人的には輪切りにして、レンチン、醤油、おかかでシンプルに食べるのが大好きなのですが、家族には流石に、、、という場合はオクラのお浸しはどうでしょうか?
オクラのお浸し
材料
オクラ、塩(いたずり用)めんつゆ、活節、ショウガお好みで。
- オクラは種類によりますが、結構ちくちくの産毛?があるので、塩でいたずりとして、できるだけ落とします。
- オクラのがくの所をくるり剥きます。切り落としてもいいけど、少し見た目と、場所により中の種が出てくるので、剥く方がきれいです。
- レンチンで火を入れます。湯がいて火を入れてもいいです。
- めんつゆをお好みの濃さに水に溶いてその容器にオクラをお浸しにします。
- 一晩程度置く方が味が染みますが、半日程度でも食べれます。(ここはめんつゆの濃度で判断してください)
- 仕上げにお皿に盛り付け、鰹節、すり下ろししょうがを添えると立派な一品です。
まとめ
オクラもそんなに私は害虫に悩むことはないのですが、この葉巻虫だけは毎年の問題になります。
そして新芽を食べて、葉っぱをボロボロにするのもこの虫かな?と思っています。
☆違っていたら申し訳ありません。
目に見えにくい物なので、居そうな気配がするとロハピで撃退すると多分いなくなっている印象。正直、防虫ネットが一番いいと思うのですが、オクラの花が好きなので、そのままいつも開放して育てています。
オクラは育ててわかるのですが、肥料を好む野菜のようです。
少し油断するとすぐ花が上の方で咲くので、時折化成肥料や鶏糞などで対応しています。
まだまだ暑い日が続きますが、このままお手入れを続けておいしいオクラを食べましょうね。
本当に暑いのでお体に気を付けてくださいね。
他のオクラ記事です↓
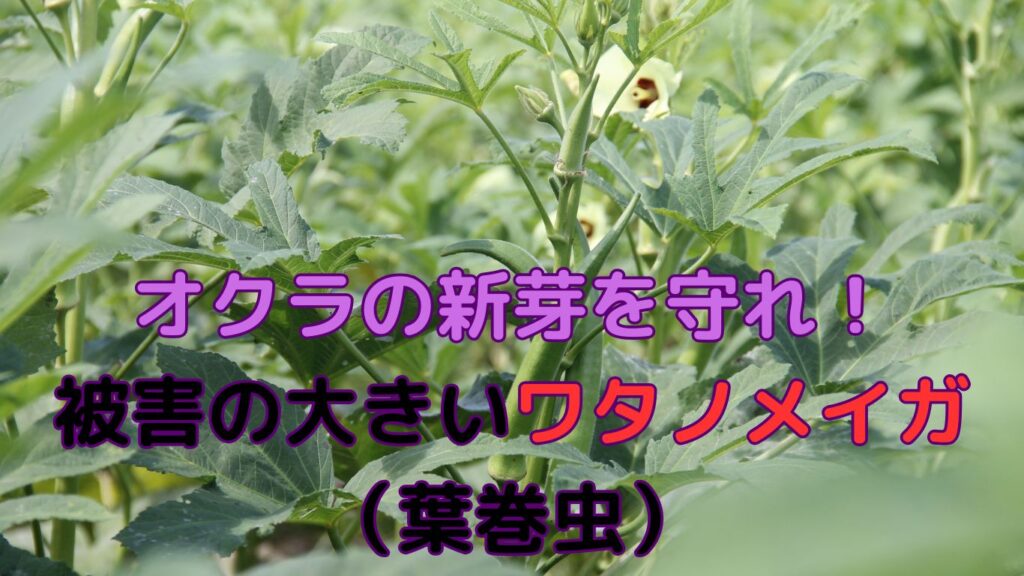


コメント