こんにちは、家庭菜園日和ですね。天気もいいし、気候もまだまだ外で作業しやすいです。
そんな家庭菜園ライフですが、そろそろ虫に困ってませんか?
私は絶賛困り中です。ヨトウムシが、、、、。あいつが、、、。でもできるだけ市販の農薬は使いたくない。そんな私が色々調べてみました。
初めからの対策
家庭菜園は楽しい収穫。イチゴ、トマト、ナス。楽しいですよね。初めは小さい花から始まり実になって、だんだん大きく、色ついて。でもそれを台無しにするもの!それは虫!病気!
大丈夫!対策方法はあります。

病害虫に強い品種を買う。
品種改良や、接ぎ木により病害虫に強い苗があるので、初心者の方には特におすすめしたいです。
お値段は張りますが、手間が圧倒的にかかりません。
でも、どうしても生き物ですので、確実に病害虫にかからないわけではありませんが、ぐっと被害を下げてくれるはず。
無理に狭い状態で植えない、育てない。
病気や、虫は環境の状態もとても重要です。
狭い範囲での植え付けは、そもそも根からの栄養や、葉の光合成が十分にできることが少ないです。
またその状態では風通りも悪い、野菜の抵抗力も低い状態で育つようになります。そうなると、やはり発生する、病害虫。
野菜に求められる間隔はいろいろ違いますが、推奨される間隔を取り健康に育ててあげてください。
適切な量の肥料を使う。
肥料もその野菜により必要な量が違います。
そして、ちゃんと必要な量はパッケージなどに明記してますので、守るようにお願いします。
野菜も人間と同じです。
肥料(ごはん)を入れてもメタボになるだけというか、植物の場合、肥料焼けなど生育障害がおこることもありますし、その肥料で害虫を呼び寄せることもよくあります。
観察をして病変を見逃さない。
虫や病気の原因は、勝手に家庭菜園に忍び寄ります。
適時観察を行い、病変にすぐ気を付けれるようにすると、すぐ対策をとることができますので、安心です。
どんな害虫がいるか?
そもそもどんな虫がいるのでしょうか。
☆虫苦手な方はここの症は飛ばしてくださって大丈夫です。
害虫は家庭菜園にとって基本良くないですよね。
まず考えられるのが食害。食べてしまうこと、そして病気を連れてくることなどが本当に困ります。
食べられるだけでも嫌なのに、病気が発生すると何かしらの対策を講じない限り最悪全滅にもなりかねませんから。
野菜、ほぼ植物全般にいる害虫。
アブラムシ
特に、アブラナ科、ナス科と言われていますが、結構な野菜、花、植物全般につくことがあるのではないでしょうか?家のバラにもびっしりついて嫌な気分です。
小さい緑色の粒のような虫です。気が付くといっぱい増殖するクローン。
茎などから植物の栄養を吸収して、弱らし場合により病気を運んできます。
アブラナ科によく来る害虫
アオムシ
(キャベツ、ブロッコリー、白菜、小松菜、ダイコンなど)
モンシロチョウの幼虫のあおむしが食害しに来ます。
食欲が旺盛で、気が付くと葉っぱにすごい大きな穴がぼこぼこ空いてきずくこと多いです
野菜や花などの若い苗を切り倒す害虫
ネキリムシ
夜行性なので、夜の間に活動して、大切な植えたばかりの苗や育ってきた苗を切り倒していく、、、。(葉っぱとか食べていないのも激おこです、何のために伐採したのか!)
朝私たちを絶望の淵に落としてくる憎いやつです。
伐採した苗周りの近い土を掘ると黒~茶色の芋虫が居たらそれが犯人です。
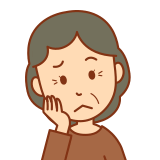
ネキリムシは私の中で一番憎い虫です。
今年は被害が特にひどく花は出てきた双葉のひまわりからトマト、ジャガイモも伐採されました。
番外に蟻
この蟻は種類により、野菜の根っこに巣をつくる種類のものがいますが、基本野菜に無害のように扱われます。が!違います。
上記厄介なアブラムシの騎士のような動きをするのでアブラムシが爆発的に増えることがあります。(アブラムシを食べるテントウムシ対策のあり)
このアブラムシが増えることは歓迎すべきことではありませんので、注意です。
他にも色々害虫はたくさんいますが、対策が違ってきますのでまず原因となる虫を特定して対応してみてください。
病害虫に対しての物理的対策
防虫ネットや、マルチで予防する
物理的に虫を通さないので対策としては十分有効な手段となりやすいですが、問題は夏に高温になりやすいことと、風通しの問題が出ることがあります。
そのため野菜の状態を観察して異常をすぐわかるようにしたいですね。
野菜周りの雑草の除去
雑草が生い茂るような環境は野菜にとっていい環境とは言えないようです。
雑草が病気や虫を招き入れることもありますし、せっかくの肥料も雑草の養分にするよりは野菜に与えて大きく育てたいです。
家庭にある食品でで害虫対策
ちゃんとお世話をして観察して予防して万全の体制を整えてもある日病害虫が発生することがあります。
虫が出た!病気になった!でも市販の薬を使いたくない。そんなときは家庭になる食品でもできることがありました。身近なもので対策をしていきましょう。
重曹
食品としてではなく、掃除用具としておいているご家庭も少なくないのではないでしょうか?
うどん粉病対策として水で希釈してスプレーすることのほかに蟻、ナメクジ対策として使います。
酢
酢に含まれる酸が虫の忌避に繋がります。
濃度が高いと野菜自体にダメージを与えられますので、濃度調整をお願いします。
牛乳
アブラムシに効果的です。
牛乳をアブラムシにスプレーするとその膜により窒息します。
牛乳の場合原液でもスプレーして大丈夫のようですが、しばらくしてたっぷりの水で洗い流してください。
カビや他の病気の原因になることもありますし、何より匂います。
唐辛子、ニンニク
虫に対して刺激物であり、忌避されます。
固形ですので、お酢や、アルコールなどに成分を抽出して水で希釈しスプレーすることおが一般的になります。(300倍程度の希釈で)
刺激物になりますので、目や鼻など粘膜に当たらないように特に十分注意して散布してください。
☆自然農薬はやはり化学農薬より緩やかで効果もすぐに!ということはないようですが、野菜の状態を観察し、適時繰り返し使用してみてください。
☆予防の場合は野菜の状況をよく観察して定期的に散布してください。
☆害虫の種類により効果は変わります。
☆希釈して使用しますが、初めての場合は少し低めの濃度で行って様子を見てください。
コンパニオンプランツ対策

コンパニオンプランツとは近くに植えることでお互いにいい影響を与える植物のことになります。
効果としては、特定の虫や病気に対するもの。野菜の風味がよくなる。成長がよくなるなどです。
マリーゴールド
コンパニオンプランツとして一番聞いたことがある植物だと思います。
オレンジ色と黄色のお花で一部を除き一年草です。
種から植えても2か月ぐらいで開花することが多く、その独特の香りが病害虫を防ぐといわれています。
センチュウ、コナシラミなどに効果があるといわれています。
ニラ
独特な香りで、大好きな野菜でもありますニラもコンパニオンプランツとして植えることができます。
ニラ自体にもほぼ虫は湧きません(私は今まで一度もいたことがありません)
種から育てて2年目~ぐらいから十分に収穫できるし、簡単に増えるし、その上この独特なにおいで、害虫を抑制してくれます。でも、イチゴとは相性が悪いようですので注意。
畑に植える場合には少し注意を。お花の水仙と間違えて毎年食中毒を起こす事件があります。
ぱっと見は水仙の葉っぱとニラは似ていますので、間違えることのないようにしてください。
水仙はきれいですが、食べれません!
ネギ
ネギも有名なコンパニオンプランツとして有名ですが、上記以上に注意が必要な野菜でもあります。
キュウリや、ナス科の植物とは相性がいいようですが、マメ科や結球するようなレタス、キャベツなどと混植を行うと結球しなかったり育ちが悪くなるようです。
でも、虫よけ効果は私の中でとても強いイメージ。ネギに虫がついているところをみたことがありません。
まとめ
折角の家庭菜園で科学的な農薬を使わず頑張って、虫が~、病気が~という問題が発生した方も多いはず。
もともと病気や虫に強い苗を購入したり、物理的に虫が近づけないようにネットで囲う、マルチを敷く、他には肥料や水を適切に行うことで病害虫を抑制できます。
また、病害虫が発生してもご家庭でよく見かけるもので予防や駆除する方法もありました。
植物には色々な効果を持つものもいるので一緒にコンパニオンプランツとして育てるのも良い方法です。
今年の夏は実り多い素敵で楽しい家庭菜園ライフを楽しみましょう!!



コメント