こんにちは
紅葉の葉っぱもところどころ落ちつつあり、朝夕の寒さもなかなか厳しい季節になってきましたね。
大人になると、ほんとうに一年早いです。
何なら一か月も早くて、一週間ぐらいの気持ちです。子供のころは夏休みの初めは永遠かと思うぐらいかがかった印象です。半分過ぎたらすぐですけど。
そんな季節の巡りですが、その季節を感じる野菜の一つの春の味覚なスナップエンドウ育ててますか?
現在結構大きくなりすぎていませんか?
実は冬越しスナップエンドウは大き過ぎると、問題が起こるんです、、、、。
ちなみにスナックエンドウとスナップエンドウは同じものですが、農林水産省的にはスナップエンドウが正式になるようです。
スナップエンドウの概要など

スナップエンドウは主に秋まきと春まきが主流になります。
秋まきは10月ぐらいから撒いて、冬を越して育てる方法で、春まきは1.2月に種まきを行い、育てる方法です。
必要物品は種類によって支柱の高さや有無が変わってきます。
つるなし
背丈が80センチ程度に成長するものが多い。支柱もその程度で大丈夫で、ベランダや省エネスペースで育てやすい。
つるあり
大きく育つと2メートル程度になることも多々あり、長めの支柱とネットがほぼ必要になる。畑などまとまったスペースが必要。
スナップエンドウ、きぬさや、エンドウ豆、グリーンピース、豆苗とかなに?同じ?違う?
エンドウ豆は食べたことがありますか?

私が真っ先に思いつくのは主にスナックとして加工されたお菓子は良く食べますが、それ以外は思いつかない~と思っていました。
しかし、スナップエンドウ、きぬさや、グリーンピース、豆苗は基本的に同じエンドウ豆なんです。
基本的には、どのタイミングで収穫して食べるか?が大きな違いになります。
豆苗はエンドウ豆の新芽です。リボべジに優秀な野菜ですし、値段も工場野菜の為ほぼ変動が少ない優秀な野菜です。頑張れば2回ぐらい水だけで収穫できてコスパも栄養もいい野菜です。
さやえんどう、きぬさやは、育てて花が咲き、さやができて中の豆が成熟まだしていない時に収穫します。そのためさやごと柔らかく食べることができます。薄いですので、春先の煮物などにアクセントとして添えられることも多い野菜です。
スナップエンドウはきぬさやより成長させて、さやが固くなる前で、中の豆が大きくなったときに収穫します。甘味が強く感じることができて、私は一番好きです。
1980年代にアメリカで開発された比較的新しいエンドウの品種です。
グリーンピースはスナップエンドウをもう少し成長させて十分に豆が成熟して少しさやに皺ができたぐらいで収穫します。
さやは食べることは難しいですが、ぷりぷりのエンドウ豆は豆ごはんに、煮物に大活躍です。給食の豆ごはんが個人的グリンピースの最高のご馳走でした。
エンドウ豆は完全に成熟したものになります。
グリンピースより少し硬めですが、その分保存もでき加工品でも食べたことがある方も多いはず。和菓子の豆大福や、みつまめはこのエンドウ豆から作られています。おいしいですよね。
それぞれ、その食べ方に適した品種改良のエンドウ豆がありますので、目的に合わせて品種をお選び育ててみてくださいね。
冬越しの必要性とスナップエンドウの特性
春でも、秋でも同じような時期に収穫ができるならば春でいいだろうになぜ、リスクある冬越しをスナップエンドウさせるのか?と考えたことはありませんか?
私はあります。
実は、スナップエンドウは冬越しをさせることにより、冬の季節を経験させて、そして期間を長く持つことにより、根はりを良くさせて春の収穫を増やす目的があります。
苗を冬の寒さにさらすことで、その刺激で花芽が付きやすく、苗も上部になる傾向があるため、冬越しさせてます。
また、スナップエンドウ自体が冷涼な気候を好む野菜ですので、春まきでは地域によりますが、育ち切る前にひどく気候の気温の高さが来てしまうと収穫量が単純に落ちてしまうことも考えられるため、早めに苗を育てる方法が確立したのかもしれません。
ここら辺はお住いの地域が温暖地域か、そうでないかで違ってきそうですね。
(種袋の地域の種まき時期などを参考にしてくださいね)
スナップエンドウが冬前に育ちすぎた時の対処法

冬越しスナップエンドウの場合は、成長しすぎると、いかに冷涼な気候を好むスナップエンドウでも、寒波や霜などにやられる可能性が高くなります。
その為、10センチ程度で冬を越すことを推奨されていますが、相手は自然と野菜。
思い通りにいかないことの方が多いと思います。
そろそろ寒くなりそうだから、水やりやめた、とかで成長をコントロールできるものでもないですし、でもそのままだと、真冬の気候に適応できなく枯れたらどうしよう、、、。なんて思いも出てきますよね。
私も初めのスナップエンドウ育てたときは良く思いました。
良い感じで育っているけど、これ以上は10センチ超えちゃう、、と何度も。
お住まいの地域によりますが、私の場合ですが結構15センチ以上でも枯れることなく育てて春においしいスナップエンドウができましたので、そこまで厳密に考えなくてもいいかもしれません。
(お住いの地域の寒さによりますので、違いが出てきます)
スナップエンドウの寒さ対策は?
アーチ支柱などを使い、不織布、寒冷紗などで霜や寒さから守るためにトンネル様に保護する。
藁などで全体や株元などを保護する。
などが主な対策になります。
期間としては、12月に入り寒さが厳しくなるごろまでには行います。
冬は突発的な強い風が吹くこともありますので、トンネルなどは風に飛ばされないように、固定はしっかりと行う方がよいです。
保温以外では大きくなりすぎたため切り戻す方法もあるかと思いますが、個人的には上記寒さ対策でいいような気がします。切っても脇芽で育つでしょうが、できれば切りたくないですよね。
また、支柱の立てる時期ですが、余り早いとそれを伝い上にうえにと伸びたがり、余計に高さが出る傾向がありますので、支柱はある程度年を越した後でも遅くはないと思います。
霜の悪影響は表面の葉っぱや茎だけにはとどまりません。
根っこなどの株元に霜柱が立ってしまうと、根っこなどを傷つけたり、切れてしまったりする恐れが出てきます。
最悪、地上部が多少枯れてしまっても株元が元気に生きていると春先に新しい芽を出すこともあります。
まとめ
スナップエンドウなど冬越しをする野菜は寒さには強い品種が多いですが、やはり大きく育ちすぎると、冬越し失敗のリスクが高くなる傾向があります。
特に、初めて育てる場合ですと、教科書、ネット通りの10センチという大きさがとても気になりますよね。
私もそうでした。
私の場合は(一本だけですが)15センチ以上になってひょろひょろの長いスナップエンドウに年越し前になってしまい、この子は枯れる運命か、、、と思っていましたが軽く霜対策した程度で無事冬を越すことができました。
意外に植物は強いものです。
異常気象になることがままある昨今ですが、できる対策を行い楽しく春先には大きく育ったスナップエンドウを楽しみましょうね。

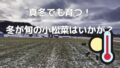

コメント