こんにちは。
寒さがどんどんと押し寄せる季節になってきましたね。
我が家では炬燵派閥に属しているのですが、流石に寒くて空調も始めました。
出来れば電気代の関係で、もうしばらくは様子見を行いたかったのですが、18度を下回るリビングでしたので、、、。
偉い方々が室温などが18度以下では、体には負担が出てくるとの見解をあげてくださっているので健康一番で18度が私の中でラインになっています。
一応としては18度以下で血圧上昇、循環器、呼吸器リスクUP,不眠などに影響があるようです。
個人的にはそれ以上に風邪ひきそう!今年はなんだかインフルも多いような気がしますし。
そんな寒さの中でも寒さに強い小松菜育ててみませんか?唐突!
もちろん自分の体調一番ですが、小松菜は栄養豊富でいつもあればうれしい野菜ですので、私も現在育てています。
私が目指すはお正月のお雑煮ですので、小松菜さんには頑張って育ってもらいましょう!
小松菜の基本情報と特性
スーパーなどでおなじみの小松菜です。
名前の由来は江戸時代に東京の小松川付近で育てられて、現在はほぼ一年を通して販売されています。
緑黄色野菜で、栄養価も高く、寒い冬には特においしさUPと言われています。
アブラナ科で旬は冬、この季節になります。
適正気温は20度前後ですが、真冬でも工夫次第で育てることができます。
暖地ではほぼ年中育てることができますが、真冬の厳しい状態ですと成長とまりますし、霜対策は葉物野菜ですので必要になります。
日光を好む野菜ですので、冬場はできるだけ日向の多い場所の方が成功します。
また、季節により育成機関が変化します。春まきですと、一か月程度で収穫できますが寒い時期ですとやはり成長スピードは緩やかになり収穫まで2.3か月ほどかかります。
しかし、その分寒さに当たり甘みが増し、小松菜特有の苦みを比較的感じにくくなり、旬の冬の小松菜は特に美味しい野菜だと思います。
栄養もほうれん草に引けを取らず、なんといってもあく抜きなどの手順もいらず、調理しやすい野菜です。
真冬における小松菜の栽培方法
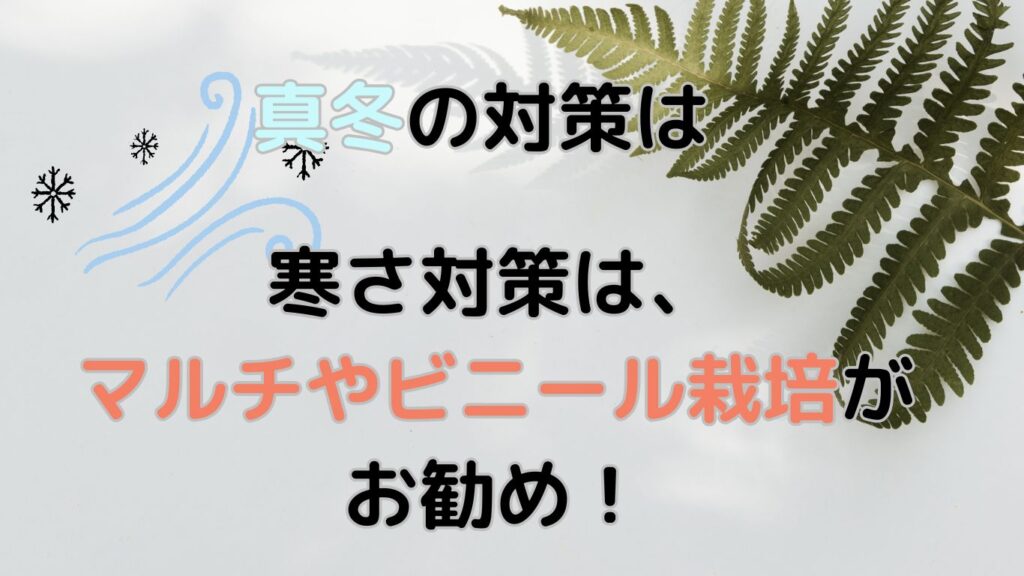
小松菜は旬が冬で寒さにも強いですが、初めの種選びでも寒さに強いものを選び失敗を減らすことをお勧めします。
でも、小松菜は本当に寒さにはもともと強いので、100円均一の手に入れやすいタイプでも発芽して、去年は寒い間でも育ってくれました。(現在私が育てているものは100円均一の小松菜です)
寒さ対策をする
真冬での小松菜栽培を成功させるにはできることならば、寒さ対策をした方がいいです。
寒さに強いことと寒さの中でも必ずしも成長する、というわけではなく、その寒さの中で成長がほぼストップしてしまったり、少し暖かくなるとトウ立ちがおきやすくなります。
少し資材が必要になりますが、マルチを行うことやビニールトンネルを使用するなどを行いできるだけ温度を保つことでおいしい小松菜が栽培できます。
家庭菜園でのマルチング
目的)
地温をあげたり保温効果がある
水やり、雨などによる土壌の栄養の流失を少なくする
土壌の乾燥を防ぐ
水やりや雨による泥はねを防ぎ葉っぱの汚れや、病気をできるだけ予防する
色により雑草予防などもあり
などなどが期待できます。
今回のマルチの一番の目的は地温の保温効果を期待してマルチを行います。
マルチ資材は何でもありますが、個人的お勧めはやはりビニール黒マルチです。
透明マルチは地温を上げやすいですが、黒マルチは地温をあげて保温効果も多少あります。この冬場には重宝します。
そしてマルチにもともと穴のあるタイプ以外にも、穴が開いてないタイプは筋蒔き時などに使うことはできます。
土づくりを行い、マルチを張った後に筋蒔きを行いたい場所に切り込みを入れてそこに種を蒔きます。
後はたっぷりの水やりを行ってください。
その後はいつもの小松菜を育てるときの通りにお世話を行います。
マルチを使っていると普段より水の蒸発は少ないですが、全然水やりを行わないことは難しいと思います。
水やりは適度に雨が降る場合は必要ない場合がありますが、土が乾燥し続けている場合はそのたびに水をたっぷり与えてください。
ビニールトンネルを作る
目的)
保温を行い作物の育成を促進させる
冬場などの霜対策
病害虫の防止
急激な強い雨や、風対策(あまりひどいと難しいですが)
急激な温度変化を和らげる
などになります。
マルチの項目同様ですが、今回は全体の保温が主な目的で用います。
様々なビニールトンネルのやり方がありますが、育ててる場所や規模で決めてみてくださいね。
育てる場所によりますが、やはり冬場は冷たい風が吹くことが多いので、ビニールを飛ばさないようにしっかりと補強をしてください。
今回の目的は季節的に防虫ではないので、裾処理はそこまで厳密でなくてもいいかもしれません。
しかし、温暖な虫が多い地域や、特定の冬場に発生する虫を防除したい場合は裾も注意して防虫対策してください。
最近100均一に行くことがありましたが、アーチ支柱も販売されていたので、私は現在100円の支柱を使ってますが十分頑丈です。
ビニール資材は、ホームセンターの方が豊富にありました。
プランターを使った真冬の小松菜栽培
プランター栽培ですと、畑栽培より保温が簡単になりやすいです。
お手持ちのプランターに支柱用ホールがある場合はそこに支柱をセットし、ビニール資材で保護を行うことができます。
プランター栽培ですと冬の日光が当たりにくい場所を避けて移動もできますので、真冬の小松菜栽培の難易度が下がりますね。
水やりは少し注意してください。
乾燥気味の冬ですので、少し油断をすると土の量も少なめのプランターはすぐに水切れを起こしやすいです。
たっぷりと土が乾燥したときは与えてください。
理想の収穫時期とその理由
冬の時期の栽培は他の時期と比べて成長が緩やかで、その分収穫時期も遅くなりますので、その分収穫時期を遅らせすぎると今度は春に花が咲きトウ立ちということが起きます。
ですので、成長具合によりますが20センチ程度に成長したり、育成90日前後を目安にするといいと思います。
少し小柄な小松菜での収穫になるかと思いますが、十分おいしいサイズです。
お味噌汁に、お浸しに、おいしく調理してくださいね。
病害虫対策と注意点

冬に気を付ける病害虫の種類
冬場は夏場や人間が過ごしやすい気温の時期よりも、病害虫の発生は本当に少ないですがないわけではありません。
一番の予防はやはり日々の観察ですので、ビニールトンネル中でも時折は観察して成功に導きましょう。
白さび病
15度程度の気温で、湿度が高めの風通しの悪い作物に現れることがあります。
葉っぱの裏などに白い錆のようなものが出て、だんだんまばらに広がります。
雨が長く続くような、湿度が高めな状態が続く場合は注意が必要です。
対処としては、農薬以外は病気が発生した株を速やかに除去することをお勧めします。
病変部分を除去して、食べることはできるようですが、気持ちのいい物ではありませんよね、、、。
ヤサイゾウムシ
成虫の体長は1センチ程度の虫です。
夏の間は休眠して本領発揮はこの真冬の間の11月から春先にしばしば発生します。
葉っぱをレースのように柔らかい部分を食害していきます。
日中ではなくに夜間に行動開始し、日中は株元にいることが多い虫です。
アブラムシ
冬場でも温かい時期より少ないですが発生することがあります。
小さな見た目ですが一度発生するとあっという間に増えますのでこちらも早期発見が重要です。
主に、小松菜の栄養素を吸収されるため育成不良や、病気の発生を起こしたりいいことはありません。最悪枯れます。
少ない状態でしたらテープで取り除く、刷毛や水で洗い流して数日様子を見てください。
数が多い場合は牛乳スプレーや、農薬も有効です。
アオムシ系
冬場ではアオムシなどいない印象ですが、地球温暖化の影響か蛹での年越しではなくちょうちょの状態で寒い時期にひらひら見かけることがあります。
温暖気候で小松菜を育てる場合は、季節関係なく防虫ネットなどで対策を行う方がいいかもしれません
ハクサイダニ
冬から春の間に活動する害虫です。
名前の通り小さな赤みがかったダニで、夏場は休眠して晩秋ぐらいから活動開始します。
名前はハクサイダニとありますが、白菜以外にも、小松菜や、ほうれん草、そこらの雑草、草木にもしばしば発生します。
小さい体ですが、作物の栄養素を吸収して、成長阻害、最悪枯らすことがあるので注意が必要です。
栄養を吸われた作物はだんだん白っぽくなりますので、そのような状況になった場合は良く作物を観察してください。
まとめ
冬は家庭菜園者としてはすこしさみしい季節です。
その寒さゆえに作物はとても限られていますし、わさわさとすぐに収穫できるものもあまりない、、、。
でも、今が旬の小松菜栽培は今からでも工夫次第でできます。
出来れば温暖な地域で、日照時間も多い方が有効ですが、マルチや、ビニール栽培を行うと、長くても2.3か月で収穫できる寒さに強い作物、小松菜です。
この頃の物価高で、特に去年の葉物野菜のキャベツ、白菜は本当につらいお値段でした。
ですが、家庭菜園で育てることができればコストも安く、そして安心安全のおいしい作物が収穫できます。
冬場ですので、比較的病害虫も少ない時期ですのでそのような虫が苦手な方もぴったりなのではないでしょうか?
私も現在小松菜栽培を始めています。正月に入れることができたらうれしいですが、これからの気候によりますね。
寒さ厳しくなるこれからの季節ですが、皆様も無理をせず楽しまれてくださいね!
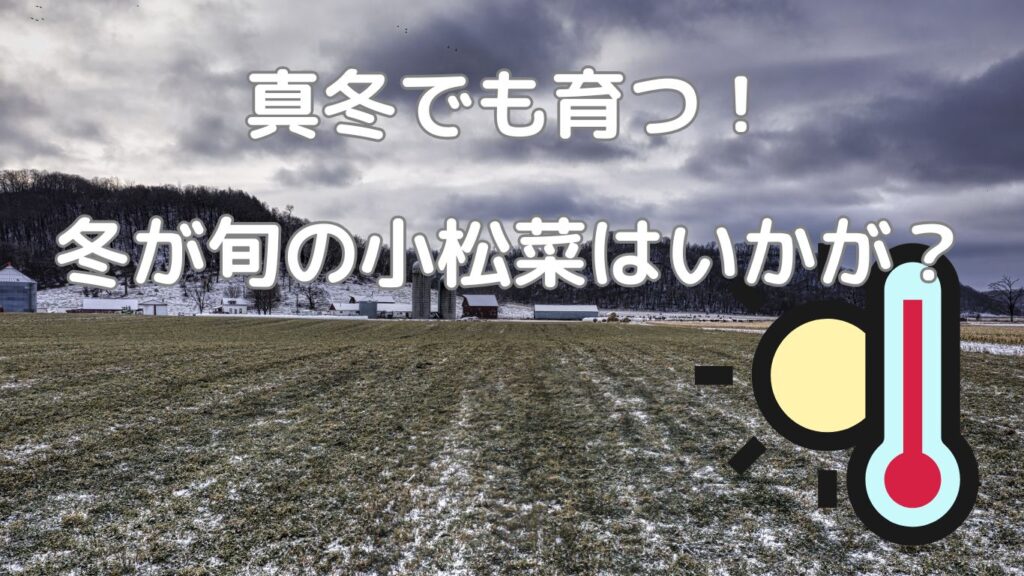


コメント