まだまだ暑い日が続きますね。
去年は本当に暑いまま、気が付けが冬が来てしまったので、今年はもう少し秋を満喫したいです。
私は秋には毎年行うことがあって、、、それはニラの株分けです。
ニラってすごく、育てやすく日々の水やり程度でもすごく増えるんです。
手間はほとんどかからないニラですが、なんだかお店のようには柔らかいものができない印象です、、、。でもポイントがいくつかありました!主に追肥と、株分けと、日光管理などです。
家庭菜園におけるニラの基本知識

ご家庭でもよく使う野菜の一つのニラです。
独特の風味がなんだかスタミナが付き、元気が出るような印象がありますよね。
栄養価も豊富で、独特なにおいの元はアリシンと言われており、疲労回復に効果があるとされています。
他にも、ビタミン、βカロテン、食物繊維なども豊富で、お肌や健康にいい野菜です。
科目はヒガンバナ科ネギ属で、野菜では珍しく多年草です。
ですので、一度植えると数年にわたり収穫できるコスパのいい野菜です。
根元三センチぐらいを残して葉っぱを使うと何度でも伸びてきて、冬以外でしたら何度も楽しむことができます。
(冬は流石に地上部が枯れたようになりますが、春先にまた生えてきます)
日当たりを好みますが、ある程度の日陰でも育ちますし、プランターでも十分収穫てきます。

私はプランターでニラを育てています。
みちみちに育ってて、本当に水と、時々の追肥ぐらいしか行っていませんが、すごく元気にいま花を咲かせています。綺麗!
家庭菜園でのニラの栽培法
一番手間がかからない方法は苗を買ってきて定植、育てる方法ですが、種でも十分育ちます。
弱酸性、水はけのいい土壌を好みますが、そんなに厳密に行わなくても十分育つ印象です。
市販の培養土をプランターに入れて、種をまくと育つと思います。
種の蒔く時期は春先3月ぐらいが多いですが、一応9月も種を蒔くこともできるようです。
生育適温は、20℃前後になります。極端な暑さ寒さは枯れることは少ないですが、育成適温時期の方が収穫量がすごく増えます。
今年の夏は本当に暑かったですが、枯れることなくピンピンしていました。
プランターで育てる場合は水切れが起こらないように少し注意すると、季節が合う時期でしたら発芽してすくすく育ちます。
種で蒔いた場合は、発芽したときにすごく密集していると、今後病害虫に強いとはいえやはり心配ですので、株間を2.3センチぐらいになるように間引きを行います。
乾燥には少し弱いというか、水がなくなってくると明らかにへにょんっと葉っぱが下がりますので、わかりやすいです。(プランターの場合わかりやすいです)
ニラを育てるための肥料と管理
肥料と追肥
肥料としては、初めの元肥料があれば十分育ちますが、種から育てる場合の初めの一年は株を育てるために9月ぐらいに肥料をあげます。
(できれば一年目は収穫せず、育てることを目的に)これを行うことにより、株を大きく健全に育てて、二年目からの収穫をより楽しめます。
二年目からは春すぎてニラが大きく育ち始めたときから、月に一回ぐらいの追肥をします。
適正気温の時期は、ニラは根元3センチぐらいを残して収穫すると、一か月しないぐらいに再度収穫できるぐらい旺盛に成長しますので、やはり追肥が大切になります。
他の管理としては株分けも重要です。
3年目ぐらいからよく見ると、ニラの株がきつそうになってきます。
このまま放置してもいいことはないので、株分けをします。
株分け
株分けといっても簡単です。
数年ニラを育てていると、株の根元が密集するので一度株をばらばらにして、再度植えたい場所に植えるだけです。
植物によりますが、繊細な植物ではこの株分けをちゃんと丁寧に行わないと枯れるのもの出てきますが、ニラは頑丈です。多少根っこが傷つこうがちゃんと育つことが多いと思います。
そこらへんも初心者向けの野菜と言えそうですね。ニラ!
ニラ育成のポイント:柔らかく育てるためのコツ
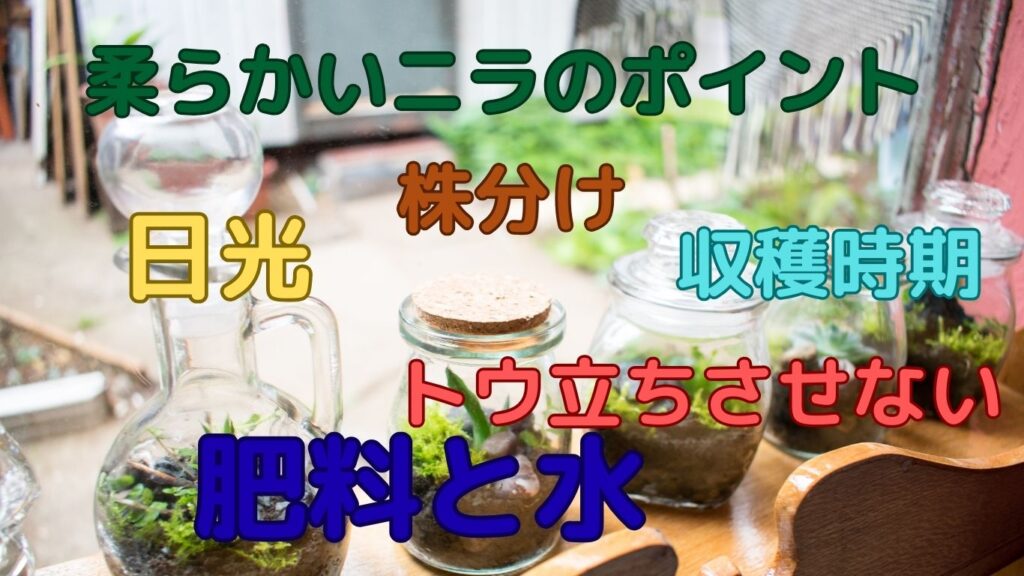
市販のニラを食べていると、自分で作ったニラがなんだか固く、細いような気がします。
もちろん農家さんのようなプロとは同じようには難しいことも多々ありますが、コツや工夫をすることでおいしいニラを作ってみましょう。
日光の量
日光は植物を健全に育てるうえでは欠かせないものですが、日光が当たるとその分だけ頑丈にも育ちます。
それが固い食感になる可能性があります。
例えば、黄ニラはご存じでしょうか?黄色いニラなのですが、これは極端に日光を避けて育てたニラなんです。
株を十分に育てて、その後通常のニラの上の部分を刈り取り、日光にさらさないように育てたものが黄ニラになります。
流通は少ないので、スーパーなどではあまり見かけることは少ないですが、和食屋さんや、料亭などで使われることが多い印象です。
味は、生でもおいしく柔らかく、甘味があるような、瑞々しいニラです。
ここまで、日光を除外しなくても柔らかくニラを栽培できますが、夏の日差しが強すぎる場合は日差しをよけ、風通しを良くするように栽培してみてください。
適切な肥料と水やり
柔らかく、おいしいニラには肥料も欠かせません。
他の野菜よりそんなに神経質に気にしなくてもニラは十分育ちますが、低肥料で育てるとやはり育つスピードの時間がかかり、固くなる傾向があります。
適度に、肥料を行い、葉っぱが広がりおいしく育つためにも追肥を行いましょう。
一般的には一年目は土壌管理の元肥料、肥料と9月ぐらいに株を育てるための肥料、二年目からは毎月ぐらいの追肥が好ましいです。(成長が早い季節でしたら2週間から3週間に一度でもいいと思います)
一度にドバっと肥料を与えると肥料焼けで株が枯れる可能性があるため、できれば適時の追肥が好ましいです。
株分け
種からは想像ができないほど数年でしっかりとした株になるニラですが、種以外でも株分けでニラは増やせます。
ニラを株分けを行い増やせるということは、株分けしないと込み合い、そのままでは成長を阻害する可能性があるということでもあります。
現に、三年目には株分けを勧めるサイト様が多いですが、私もお勧めします。手間のかからないニラの水やりや、肥料など以外のことで行うことが必要なことになります。
株分けをしないと、細く、固いニラが作られやすいです。
株分けはいつでもしていいものでは無く、冬から春までに行うことがいいです。
作業がしやすいように地上部を5.6センチぐらい残して切り取り株分けを行います。
そしてざっくりとスコップなどで根っこをできるだけ傷つけないように掘り返し、両手で根っこと土をほぐしてください。
一本ずつにしなくても大丈夫です。何本か束か横に並べるようにまた植え付けを行います。地上部は数センチ残して、植え付けを行ってください。
暫くするとまた、根っこが定着してニラが育ちます。
収穫のタイミングと方法
ニラは収穫のタイミングは人それぞれ、必要時に使えるのが家庭菜園の醍醐味ですが、できるだけおいしく柔らかくニラを食べるためには、早めの収穫がお勧めです。(20センチぐらい)
長く育てていると、その分だけ日光に当たり続け、固くなる傾向があります。
また、家庭菜園では春ごろのニラが柔らかい傾向にあります。
収穫してもすぐに生えてくる印象がありますので、収穫時期になったらとりあえず収穫して、冷凍保存私はしています。
保存袋はできるだけ密封できるものを使い、洗って水けを取り、軽く空気を入れて冷凍するとぱらぱらで保存しやすいです。
そのあとは、必要時チジミや、鍋に使えます。おいしい。
トウ立ちして来たら
トウ立ちは、ニラが自分の花を咲かせ、子孫を残すために種を作ろうとします。
この状態になると、葉っぱも硬くなり、風味もだんだん落ちてきて、目指す柔らかくおいしいニラとは言えない状態になります。
一日の日照時間や、肥料が少ない、株が成熟してきたなどの条件はありますが一般的に6月から8月に花芽を付けることが多いです。
対策としては、出てきた花芽を咲く前に切り取る。他には栄養不足に気を付けるなどがあります。
ニラは、短いつぼみのままの花のつぼみは食べることができます。葉っぱより甘味があり、高級食材ともいわれています。
スーパーなどでも売られるものでもないので、家庭菜園の楽しみとしてもニラの株を弱らせないためにも花は早めに収穫したほうがいいです。
☆今年はニラの花はかわいいので私の家では観賞用に育て中です。かわいい。
ニラと水仙
水仙を庭で育てていて、その近くにニラを植える場合は注意が必要です。
毎年ニュースでも見たことがある方もいると思いますが、ニラと水仙は間違えやすい見た目をしています。
ニラと間違い水仙の葉っぱを食べてしまい、食中毒にあるような事件です。
匂いはニラ独特のにおいがありませんが、水仙の葉っぱは外見がよく似ています。
比べてみると、水仙の葉っぱの方が肉厚で、幅広い印象がありますが、単品だとわからないぐらいの違いです。
明らかなのは、ニラには独特のにおいがある、ということですが、環境によりにおいが少ない、匂いがしないニラも存在します。
ですので、やはり水仙の近くに食用にするためのニラは育てない方がいいと思います。
個人的にニラのお花は白くポヤポヤしててかわいいので、観賞用なら水仙の近くでも問題は無いように思いますから。
他にも家庭菜園で少し危険なもの
青い未熟なトマト、ミニトマトは食べられる?知っておくべき危険性と対処方法
よくある疑問:ニラの栽培に関するQ&A

多年草のニラですが、じゃあ多年草ってずーっと同じ場所で水をやっていればずーととることができる?
A,多年草と言えど、ニラは3~5年と言われています。
しかし、ニラは自分の株を増やしていき増殖しますので、3年ぐらいでの株分けでそのままニラを育てることができます。その後も適時株分けをしていくとずーっとそだてることができそうですね。
ニラの株分けは必要か?
A,上記のこともあり、できるだけ株が込み合って来たら株分けしていくのがお勧めです。
込み合ったままでも栽培は続けることができますが、やはり栄養不足、通気性が悪いなどで、病害虫の可能性が上がりますし、細く、収穫も減ります。
株分けは他の野菜より簡単ですので、思い切って頑張ってみましょう。
寒くなったら枯れた!
A,枯れていません。安心してください。
地上部分の葉っぱは枯れたように見えますが、ちゃんと根っこは生きています。
水やりに関してですが、地植えはそんなに気にしなくていいと思いますが、プランターの場合はあまりにあめが降らない日々が続く、土が乾燥しすぎている様な場合は湿らす程度に水やりをしてあげてください。
びしゃびしゃにいつもしていると根腐れを起こす可能性が出ますので、あくまで控えめに、水やりをしてあげてください。
無事、生き残れば春先に綺麗な緑色のニラがにょきにょき生えてきます。
一年目は食べることができない?(種から育てる場合)
A,できるだけ、できた栄養は株を太らせるために食べないことが多いです。
ですので、食べるのは2年目からと言われています。
が、正直家庭菜園です。好きにしてもいいのではないでしょうか?

現に私は一年目の秋の最後らへんに少し食べてみました。
結構細いニラでしたけど、ちゃんとニラのにおいがして、当たり前ですがニラだったんだな~。と少し感動。
楽しみましょう!!
まとめ
ニラは多年草で本当に育てやすい野菜です。
栄養価も高く、年に何度も収穫ができます。
でも、育てていると、繊維質で固いような、、、。スーパーのニラと違いが気になることがありますよね。
ニラは育て方で、瑞々しく柔らかいニラを作ることができます。
日光は当てすぎないように、適時の追肥と、水やり。そして株分け、トウ立ちの管理です。
収穫時期を延ばすとその分固くなりやすいので、20センチ程度をめどに収穫することも大事です。
多年草なので初めの一年は株を育てる、二年目以降は適時追肥を行い収穫、三年目には株分けを行うという年単位のスケジュールです。
私が育てた上では虫が付いたことが無いので、本当に簡単です。薬味に、チジミに適時収穫して何度も楽しみましょう。
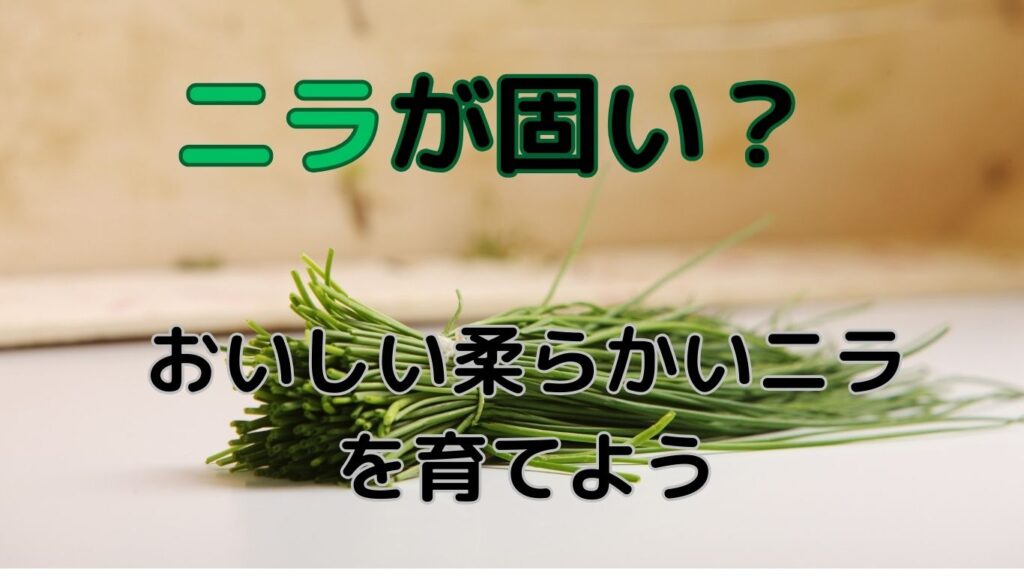


コメント